
- 個人事業主から法人化したら、社長の社会保険料の負担はどうなる?
- 半分は会社負担になるってどういう意味?
- 結局お金は毎月どれだけ出ていくの?保険料の計算方法は?
個人事業主から法人化すると「社会保険料は会社と個人が半分ずつ負担するかたちに変わる」という話を聞いたことがある方も多いと思います。
↑これ、はっきりいって「?」な感じがしますよね。
日本の社会保険の仕組みは「世界で一番ややこしい」といわれるぐらい複雑にできているので、慣れない方は理解しにくいのが普通です。
ただ、社会保険料は毎月支払うものなので、損はしたくないですよね。
せっかく事業を法人化するなら、損をしないように社会保険の仕組みをきちんと理解しておきましょう。
この記事では「個人事業主が法人化した場合、社会保険料の負担がどのように変化するのか?」を簡単にわかりやすく解説します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
「社会保険料の会社負担は半分」の意味とは?

まず「社会保険料の会社負担分は半分」←これの意味について説明しましょう。
例えば、毎月支払う社会保険料が10万円だったとしたら、5万円だけが会社の経費として処理できると言うことですね。
経費が増えればその分だけ利益が減り、税金も安くなると言うわけです。
個人事業主は社会保険料を経費として処理することはできませんから、事業を法人化することのメリットの1つということができます。
会社負担が半分になる「社会保険料」はこの3つだけ
ただし、半額負担となるのは「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険」の3つです。
そもそも社会保険とは、
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 労災保険
- 雇用保険
の5つをまとめた総称です。
このうち健康保険、厚生年金保険、介護保険については、労使折半といって会社と社員とが半額ずつ負担することになっていますよ。
法人化した後の社会保険料の計算方法

まずは標準報酬月額と等級を知ること
社会保険料を確認するには、まず自分の標準報酬月額と等級とを知る必要があります。
健康保険は50等級、厚生年金保険は32等級に分かれていて、給与額によって区分されます。
この等級によって保険料の負担額が変わるので、とても大切な情報なんです!
「保険料額表」をチェックしよう
加入している健康保険組合もしくは協会けんぽホームページや、日本年金機構ホームページで、「標準報酬月額表(保険料額表)」をチェックしてみましょう。
自分の給与額のところを見ると、標準報酬月額と等級が書かれているはずですよ。
たとえば、給与が290,000円~310,000円の人は、
・標準報酬月額→30万円
・健康保険→22等級
・厚生年金保険→19等級
ということが分かりますよね。
「折半額」で負担額が分かる
同じ行に、「全額」「折半額」という欄があります。
「全額」は会社負担分と本人負担分を合わせた額で、「折半額」は本人が負担する額のことです。
40歳から64歳の人は、健康保険では「介護保険第2号被保険者」に該当するので、この欄を見ましょう。
これで社会保険料の負担額が確認できました。
社会保険料の計算方法

では、その社会保険料はどうやって計算されているのでしょうか?
社会保険料の折半額は、それぞれ「標準報酬月額×保険料率÷2」で計算できます。
保険料率を踏まえ、どう計算されているのかを具体的に試してみましょう。
ここでは、先ほどのように標準報酬月額が30万円の場合で計算していきますね。
健康保険料の計算方法
健康保険率は加入している組合によって違いがあったり、協会けんぽなら都道府県別でも違いがありますが、
令和5年の健康保険料率はだいたい10.00%なので、それで計算してみると、
30万円×10.00%÷2=15,000円
が、標準報酬月額30万円の人の折半額となりました。
病気やケガをしたときに保険証があれば医療給付を受けることができるのも、健康保険のおかげですね!
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料率は全国一律で、平成29年以降、引き上げはされていません。
令和5年も18.30%となっています。
30万円×18.30%÷2=27,450円
が、標準報酬月額30万円の人の折半額です。
多いなと感じるかもしれませんが、それは厚生年金保険に加入すると同時に国民年金保険にも加入しているからなんです。
国民年金だけよりも老後の年金受給額を増やすことができますし、
ケガや病気が原因で障害が残ってしまったときなども年金給付を受けることができるんですよ。
介護保険料の計算方法
介護保険料は全員から徴収されるものではなく、徴収対象者は40歳〜64歳までの人です。
保険料率は全国一律で決められていて、令和5年は1.82%なので、
30万円×1.82%÷2=2,730円
という計算になりました。
これを納めておくことで、支援や介護が必要な状態になったときに、
グループホームを利用したり、ヘルパーさんが来てくれたりと介護サービスを受けることができますよ。
社会保険料が免除されるケース

産前産後休業期間中
会社員本人が産前42日分(6週間)と産後56日分(8週間)を休業したとき、その期間を「産前産後休業期間」といいます。
年金事務所または管掌組合へ申し出を行えば、会社負担分と従業員負担分の両方が免除になりますよ。
保険料は納めたことになり、将来受給する年金額が減ることはないので、ぜひ申請しましょう!
休業を開始した月から休業終了予定日の属する月の前月までの間に申請しなくてはいけないので、注意してくださいね。
育児休業等期間中
会社員本人が満3歳未満の子を養育するための「育児休業等期間」を取得したときも免除になります。
こちらは、休業を開始した月から休業終了日の翌日が属する月の前月までの間に、
年金事務所または管掌組合へ申し出を行ってください。
産前産後休業期間中と同じく、会社負担分と従業員負担分の両方が免除されますし、
こちらの制度も利用することによって、将来受給する年金額が減ることはありません。
「扶養家族」の健康保険料・厚生年金保険料
専業主婦や子どもなど、会社員の家族で生計を一にしている人の収入が一定額未満のときは、扶養に入れることができます。
このとき、追加の保険料はかかりません。
さらに、会社員の配偶者が20歳以上60歳未満の扶養家族なら、「第3号被保険者」という扱いになり、
配偶者本人の保険料負担がなくても、納付したものとして将来受給する年金額に反映されます。
従業員が2か所の社会保険に加入しているケースはどうなる?

会社員の場合、健康保険と厚生年金保険を2か所の会社で加入することができます。
しかし、保険証を2枚持つことはできませんよね。
従業員本人がどちらの会社をメインとするか決めて、年金事務所へ
「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出しましょう。
標準報酬月額と等級は、すべての会社の給与額を合算した額を保険料額表で確認すればが分かります。
保険料はそれぞれの会社が払っている給与額の割合で按分しますが、
難しい按分計算は年金事務所がしてくれるので、
事務所から送られてくる書類の通りに天引き・納付の事務を行えば大丈夫です!
従業員を支える社会保険の仕組み

社会保険料はばかにならないと感じるかもしれませんが、いざというときに助けられるものでもあります。
たとえば傷病手当金や出産手当金なども大きいですよね。
社会保険料のうち、「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険」の3つは会社が半分負担してくれますので、
将来や困ったときに備えておきましょう!
自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、
「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」
という状況の方が多いかと思います。
- まずは自力でなんとかしよう…
- とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
- 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…
↑こんなふうに考えながら、
コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。
ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、
少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。
なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、
税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。
(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)
注意してほしいのは、
税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。
事業や副業を始めて1年目〜3年目って、
事業者側も会計に慣れていなくて、
計算まちがいが生じていることって多いんですよね。
税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。
もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、
延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。
こういったリスクを避けるためにも、
「事業や副業を始めた最初の年度」から、
税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。
うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)
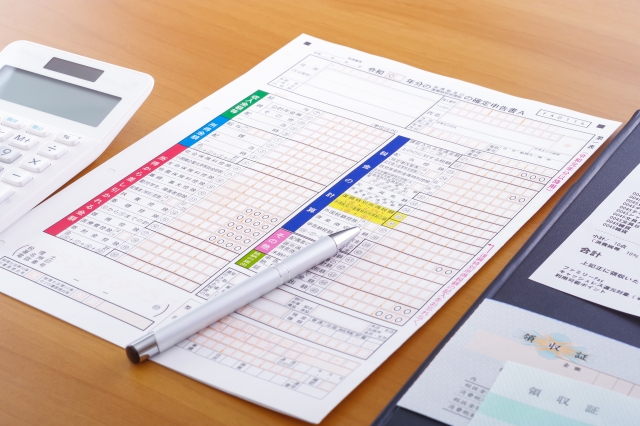
うちみたいな小さな規模のところには、
税理士なんてまだまだ早い…
↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。
私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。
「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。
ですが、小さい規模の事業者ほど、
「事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。
(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)
なぜかというと、
あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。
税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。
(これは誇張ではなく、リアルな話です)
実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや
副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、
事業を始めてまもないころに、
勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、
数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)
を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。
税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。
利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。
ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、
何年後かにいきなり税務調査がきて、
ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。
なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。
(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)
すでに事業や副業をスタートしている人なら、
少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。
「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります

税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、
使える補助金などの活用方法を教えてくれます。
利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、
「100万円以上も税金が安くなった…!」
なんてことも普通にありますよ。
創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。
(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)
節税対策や補助金を上手に活用できれば、
税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。
あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。
税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。
毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。
これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。
こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、
税理士費用の相場とかよくわからない方へ

「でも、税理士なんて知り合いにいないし、
そもそも税理士の料金相場とかさっぱりわからないんだけど…」
↑とはいえ、こんなふうにお悩みの方も多いでしょう。
そんな方は、下記のような無料税理士見積もりサイトを使うのがおすすめです。
必要事項を入力して検索するだけで、
近隣で最安値の税理士事務所を知ることができますよ。
税理士料金の相場を把握し、最安値のところを見つけましょう。
税理士って、地域によって料金相場がまったく違うので注意してください。
あなたの事業所の近所で開業している税理士事務所から、
まとめて見積もりを取って最安値の水準を知っておくことが大切です。
無料見積もりサイトなら、
顧問料金の相場や、ご自身の業種にあわせて税理士を検索できます。
- 「税理士に依頼なんて生まれて初めて」
- 「うちの事業規模で税理士に依頼していいものかな‥」
- 「とりあえず見積もりだけもらって検討したいんだけど…」
という方も安心して使うことができますよ。
↓まずは無料で税理士の料金相場をチェックしてみてくださいね。
\ 成長レベルにあった税理士が見つかる!/
