
- 自営業だとなんでも経費にできるの?
- 経費で落とす時のメリット・デメリットは?
- 経費で落とせるかどうかの判断基準が知りたい!
よく自営業の人はなんでも経費にできると思っている方がいますが、
もちろんそんな魔法のようなことは出来ません。
経費にできるかどうかの振り分けポイントは「事業に必要なものかどうか」です。
経費で落とせる?勘違いしがちな7つのポイント

経費=無料になる、お金が増えるという考えは間違い
まずは経費の考え方からです。
経費で落とせると無料になる!経費で落とせばお金が戻ってくる!
このように考える方は多いですが、経費は結局のところ出費です。
利益を出して税金を支払わなければ、お金は手元に残りませんし増えません。
節税になるからといろんな対策をし過ぎて、節税貧乏になる方が時々います。
本当に必要な経費にお金を使い、そのうえでプライベートに関わる科目などで振り分ける余地がないか?
よく考えて経費計上しましょう。
プライベートなものが経費になるのは「事業に関連する部分だけ」
経費を計上する判断基準は、「事業の売上向上のために必要な経費かどうか」です。
自営業者の方は以下のような項目を経費と勘違いしやすいです。
- 車、ガソリン代
- 飲食代、交際費
- 自宅の光熱費、通信料
注意するポイントは、プライベートか事業かあいまいなものは、
全額ではなく事業に関連する部分だけ経費にする必要があることです。
以下で詳しく解説していきます。
車、ガソリン代
営業用だけで使用する車であれば問題ありませんが、
車が1台しかなく、仕事でも家でも使用するケースは全額経費にできません。
たとえば、1週間のうち5日間を仕事用として使用する場合は、
総額の7分の5=約7割を経費にすることができます。
飲食代
取引先との打ち合わせや接待の飲食代、手土産などは経費として計上できます。
よく家族や友人との食事も計上してもいいと思っている方がいますが、
事業に関係のない飲食代は経費で落とせません。
税務調査では必ずプライベートな経費が混在していないか確認されます。
不自然に飲食代が多いと、誰とどんな打ち合わせをしたのかなど、
事業との関連性について説明が求められます。
自宅の光熱費、通信料
近年はリモートやクラウドシステムの活用が進み、自宅で仕事をする機会も多くなっています。
自宅の光熱費やクラウドシステムの利用料などは、
実際にリモートワークをした日数、使用していた部屋の面積分のみ経費にできます。
全額は経費にできないため、注意が必要です。
領収書やレシートをもらっても全て経費にできるわけではない
領収書やレシートがあればなんでも経費として計上できる!
と思っている人も多いですが、これも誤りです。
事業に関連性があるかどうか、冷静に判断して計上する必要があります。
判断に迷うときは税理士に相談することをおすすめします。
また、計上できる経費でも、領収証の内容に不備があると経費として認められません。
領収書をもらうときは以下の内容を記載してもらいましょう。
- 受け取った人の氏名
- 発行者の氏名
- 取引内容と金額金額
- 取引年月日
高い買い物をした場合は全額一括で経費にできない
単価30万円を超える資産を購入した場合は「減価償却資産」となり、
その年に全額経費にすることはできません。
資産の種類に応じて耐用年数が定められており、その年数で総額を割って経費にします。
減価償却資産とは、事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具など、一般的に時の経過等によってその価値が減っていく資産をいいます。
国税庁‗減価償却のあらまし
また月数での振り分けも必要なため、年度末ぎりぎりで購入するとその年の節税効果が少なくなります。
高額なものを買うときは、タイミングにも注意しましょう。
もうけている社長は中古ベンツで節税している?
例えば一般的な車両であれば耐用年数は6年です。
しかし中古で購入した場合は、中古耐用年数の特例で年数を短くすることができます。
たとえば4年落ちのベンツであれば、6年かけて経費にするところ2年で経費にできます。
このように中古で購入して節税している事業主もいます。
借入金を返すお金は経費にならない
借入金を返したら損益はどう変わるの?とよく聞かれます。
しかし借入金を返しても損益は全く変わりません。
借入したときに収入として経費計上しないように、
返済しても経費として計上できないため注意しましょう。
寄付金は経費として計上できるか確認が必要
寄付金についても疑問に思う方は多いです。
どこに寄付しても経費計上出来るわけではありません。
国、地方公共団体、公益法人等の指定されたところへ寄付した場合は、
経費(寄付金控除)になります。
ふるさと納税もそのひとつです。
家族などの身内を従業員にして経費扱いにする時は注意
一般の従業員ではなく家族などへ給与を支払う場合は注意が必要です。
個人事業主であれば事前に専従者給与届出書を税務署に提出しないと、
家族に支払う給与を経費にできません。
また、金額と業務内容が見合っているかを必ず検討してください。
当然ですが、本当は何もしていないのに給与だけ支払うのはNGです。
税務調査で出勤頻度や業務内容を質問されて困っている方が時々います。
気を付けて管理しましょう。
経費で落とすメリット・デメリット

経費で落とすメリットは節税できること、デメリットは会社のキャッシュ(現金)が減ることです。
詳しく説明していきます。
メリットは「節税ができる」
経費に計上する一番のメリットは、節税ができることです。
法人だと法人税が減額になり、個人事業主は所得税が減額になります。
事業に必要なものは経費にできるので、どんなものが対象になるのか調べる事が大切です。
経費になるか、判断に迷ったら税理士に相談するのがおすすめです。
デメリットは「キャッシュが減る」
経費で落とす時にはお金を使いますよね。
確実に出費が増えるため、会社のキャッシュ(現金)が減っていきます。
キャッシュは会社にとって大事な資産です。
節税になるからとどんどん経費で落とし続けると、赤字決算になってしまう時もあります。
事業が赤字になると金融機関からの信用を失い、
融資してもらえなくなることにつながるため注意しましょう。
経費は事業に必要なものだけ計上しよう

経費で落とすと節税ができるのは確かですが、
なんでも経費として計上できるわけではありません。
さらに経費で落としすぎると赤字決算になり、
金融機関からの融資が受けられなくなる可能性もあります。
経費計上の判断基準は「事業に必要なものかどうか」です。
それでも判断に迷うときは、税理士などに相談することを検討しましょう。
自営業者は、いつのタイミングで税理士に相談すべき?

このブログ記事を読んでいただいている方の多くは、
「なんらかの理由で、会計や税金の計算をなんとかしないといけない」
という状況の方が多いかと思います。
- まずは自力でなんとかしよう…
- とりあえず、今年は自分で確定申告やをってみよう。
- 税理士さんに任せるとかはまだ早い気がするし…
↑こんなふうに考えながら、
コツコツ作業されている方も多いかもしれませんね。
ただ、今後もずっと事業や副業を続けていかれる予定の方であれば、
少しでも早く税理士に税金計算を依頼した方が良いですよ。
なぜかというと、事業を始めてからだいたい3年以内のタイミングで、
税務署から税務調査がやってくる可能性が高いからです。
(特に「利益が出ている新しい企業」は集中的に狙われます)
注意してほしいのは、
税務調査って「過去の年度にさかのぼってチェックしてくる」ことです。
事業や副業を始めて1年目〜3年目って、
事業者側も会計に慣れていなくて、
計算まちがいが生じていることって多いんですよね。
税務署は、私たち事業者側のそういう「弱いところ」をついてきます。
もし税務調査が入って計算のまちがいを指摘されると、
延滞税や加算税などばく大な金額のペナルティが課せられる可能性があります。
こういったリスクを避けるためにも、
「事業や副業を始めた最初の年度」から、
税理士に確定申告を依頼しておいた方が良いんです。
うちには税理士なんてまだ早い…(←これ、危険すぎです)
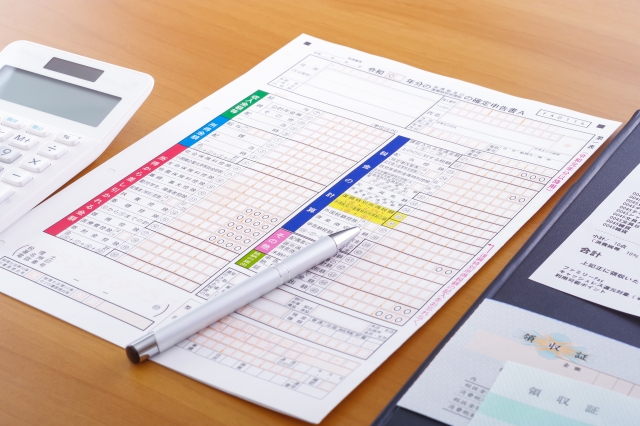
うちみたいな小さな規模のところには、
税理士なんてまだまだ早い…
↑ここまで読まれて、こんなふうに感じたかもしれません。
私も自営業長いことやってますので気持ちはわかります。
「税理士に依頼」とか、なんとなくハードルが高いですよね。
ですが、小さい規模の事業者ほど、
「事業スタートした最初の年」から税理士に見てもらう方が良いのはまちがいないです。
(すでに経験豊富な経理スタッフを従業員として雇っているとかなら別ですが)
なぜかというと、
あまり知識がない状態で、自力で税金計算するのってあまりにもリスクがでかすぎるんですね。
税金の計算をいい加減にやってしまうと、下手すると会社がつぶれます。
(これは誇張ではなく、リアルな話です)
実際、私は過去に300名以上の自営業者さんや
副業サラリーマンの方たちとやりとりをしてきていますが、
事業を始めてまもないころに、
勘違いしてやってしまった会計処理のミスが原因で、
数十万円〜100万円以上の追徴課税(延滞税や加算税のこと)
を課せられてしまった人たちをたくさんみてきました。
税金は期限までに「現金で」払わないといけないのにも要注意です。
利益が出ていても、入金がかなり先で税金の納付期限にまにあわない…ってあるあるですからね。
ほんのわずかな税理士に支払うコストを節約したのが原因で、
何年後かにいきなり税務調査がきて、
ウン十万円、ときにはウン百万円もの追徴課税をとられる…。
なんて、馬鹿馬鹿しすぎますよね。
(最近はYouTuberとかでもそういう人増えてるみたいですが)
すでに事業や副業をスタートしている人なら、
少しでも早いタイミングで税理士に依頼しておく方が絶対に良いですよ。
「100万円以上も税金が安くなった…!」なんてケースもあります

税理士は、自営業者や副業の人向けの節税対策や、
使える補助金などの活用方法を教えてくれます。
利益がかなり出ている年に適切な節税対策ができれば、
「100万円以上も税金が安くなった…!」
なんてことも普通にありますよ。
創業後1〜3年以内の自営業者だけが使える補助金とかもありますからね。
(※ 補助金=申請すれば政府からタダでもらえるお金のこと。これは期間限定なことが多いので、絶対に検討しておいた方が良いです)
節税対策や補助金を上手に活用できれば、
税理士に支払うコストぐらいは普通にペイできてしまったりします。
あと、経理のレシート整理とかってめちゃくちゃめんどくさいですよね…。
税理士に依頼すれば、こういう作業は全部変わりにやってもらえるのも大きいです。
毎日コツコツ領収書整理して、自力で確定申告…なんて早めに卒業しましょう。
これって経営者がやるべき仕事じゃないですから。
こういう「めんどうな割に1円も生み出さない作業」は税理士に丸投げして、
税理士費用の相場とかよくわからない方へ

「でも、税理士なんて知り合いにいないし、
そもそも税理士の料金相場とかさっぱりわからないんだけど…」
↑とはいえ、こんなふうにお悩みの方も多いでしょう。
そんな方は、下記のような無料税理士見積もりサイトを使うのがおすすめです。
必要事項を入力して検索するだけで、
近隣で最安値の税理士事務所を知ることができますよ。
税理士料金の相場を把握し、最安値のところを見つけましょう。
税理士って、地域によって料金相場がまったく違うので注意してください。
あなたの事業所の近所で開業している税理士事務所から、
まとめて見積もりを取って最安値の水準を知っておくことが大切です。
無料見積もりサイトなら、
顧問料金の相場や、ご自身の業種にあわせて税理士を検索できます。
- 「税理士に依頼なんて生まれて初めて」
- 「うちの事業規模で税理士に依頼していいものかな‥」
- 「とりあえず見積もりだけもらって検討したいんだけど…」
という方も安心して使うことができますよ。
↓まずは無料で税理士の料金相場をチェックしてみてくださいね。
\ 成長レベルにあった税理士が見つかる!/
